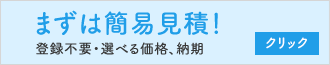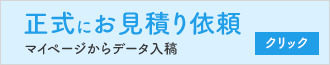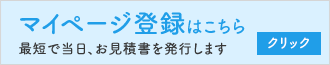議事録の文字起こしを外注してWeb会議のメリットを最大に
集合して開いていた会議をWeb会議に切り替えると、コストを節減できます。その分を議事録作成の効率化に回してはどうでしょう。内製の負荷を軽減するか、外注にするか。経営上のどんな効果を期待するかによって、判断は分かれそうです。
インターネットが社会インフラとして既に定着し、無料で始められるビデオチャットやWeb会議のツールも普及して、離れた場所にいる相手とも事実上「顔」を合わせてのコミュニケーションが容易な時代になりました。
そんな折、新型コロナウイルスの感染拡大によって外出自粛要請が始まって以後、在宅勤務に代表されるテレワーク・リモートワークの導入が一気に加速しています。
会議や打ち合わせ、研修、セミナーも、リアルな空間で「一堂に会する」のではなく、バーチャルな空間での開催を余儀なくされています。最初は違和感があるかも知れませんが、慣れてしまえば得られるものは大きそうです。

目次
1. Web会議に切り替えて節減できるコスト
Web会議は、インターネットにさえ接続できれば、自宅や自席など、どこからでも参加できるのが特長です。一カ所に集合せずに済むことで節減できるコストとしては、以下のものが考えられます。
1-1. 移動にかかる経済的コスト
電車や飛行機など移動手段にかかる費用のほか、日帰り困難な場合は宿泊費も必要でしょう。組織の規定によっては出張手当を要するかも知れません。いずれも経済的コストとして見えやすいものです。これらは会議の参加者の居場所が散らばっているほど、また、参加者の数が多いほど、さらに、会議の頻度が高いほど、節減効果があります。
例えば、いわゆる4大都市(東京、大阪、名古屋、福岡)のメンバーが新幹線で東京に集まって会議をする場合、往復交通費と日帰り困難な福岡のメンバーの宿泊費だけで1回10万円程度を要します。
なお、エコロジーの観点からも、移動は控えることが望ましいといえます。
1-2. 移動にかかる時間的コスト
モバイルワークが可能になったとはいえ、移動中は集中力を持続しようにも限界があります。また、社屋内での会議であれば、会議の場所は徒歩圏内とはいえ、席を立って移動する時間はもったいないものです。
移動にかかる時間に、会議に参加するメンバーの時間給を乗じてみると、経済的コストに換算できるでしょう。このコストも、会議の参加者の居場所が散らばっているほど、また、参加者の数が多いほど、さらに、会議の頻度が高いほど、節減効果があります。
例えば、先述のように4大都市のメンバーを東京に招集する場合、大阪往復に6時間、名古屋往復に3時間、福岡往復に11時間を要するとして、少なくとも計20時間が移動に費やされます。会議参加者の時間給を4,000円で換算すると、この会議1回あたり8万円の人件費を移動でロスしている計算になります。
1-3. 場所の確保にかかる様々なコスト
会社勤めの経験のある方は、社屋内の会議室が奪い合いになった経験をお持ちではないでしょうか。どの部署でも会議室を使いたい時間帯は重なるものです。裏を返せば、会議室は遊休空間となっている時間が多く、オフィスに会議室を増やすような設備投資は非効率といえるでしょう。また、適切な会議スペースを社屋内に用意できない場合は、レンタル会議室などを手配する必要に迫られます。
このように、会議の場所を確保するという行為は、費用はもとより時間と手間を要し、時として精神的・肉体的な苦痛も伴います。Web会議に移行すれば、こうした無駄は一掃できます。
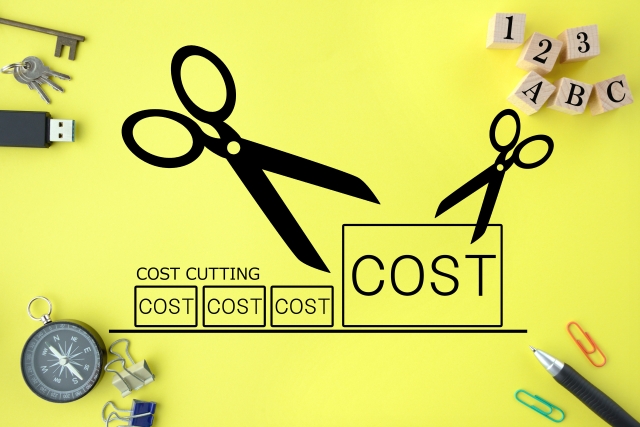
2. Web会議に切り替えて発生するコスト
Web会議システムの多くは使用料が発生します。利用人数にかかわらず月額10万円などの定額制のものもあれば、一人あたり月額数百円のライセンス料のものなど、さまざまです。
インターネットで「Web会議」を検索すると、ユーザーの支持を得ているWeb会議システムを比較しているサイトが上位でヒットします。初期費用の有無や、ランニングコストの課金は従量制か定額制か、あるいは無料プランはあるのか、といった情報を確認できるでしょう。
3. Web会議に切り替えると損か得か
参加者が一カ所に集合して開いていた従来型の会議を、Web会議に切り替えた場合の単純なコストメリットは、「(節減できるコスト)-(新たに発生するコスト)」で見積もれます。上述の4大都市のメンバーを東京に招集する会議の場合、1回あたりの移動にかかるコストの概算は計18万円でした。これをWeb会議に切り替えた場合、Web会議システムの利用料を差し引いたとしても、コストメリットは十分にありそうです。
一方、近距離の拠点もしくは同じ社屋内のメンバーによる少人数の会議では、それほどのコストメリットは見込めないことになります。
ただ、仮にWeb会議システムの利用料が、移動に関して節減できるコストを上回ってしまったとしても、Web会議への移行を断念してしまうのは性急です。Web会議がもつ議事録作成との親和性の高さを活かすことで、別次元のメリットを享受できる可能性があるからです。
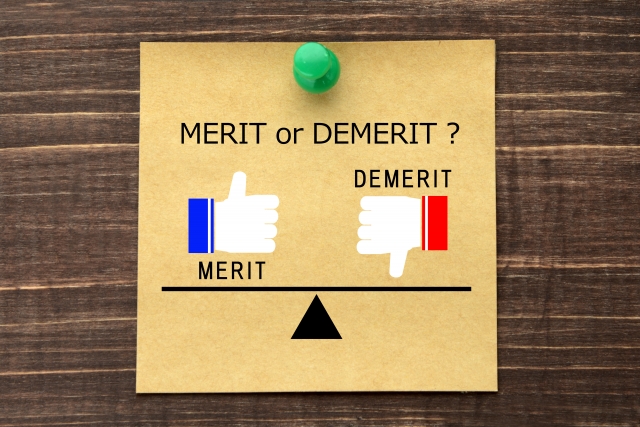
4. カギを握るのは議事録作成の効率化
Web会議が普及する以前に、移動のコストをかけてまで開いていたほどの重要な会議であれば、当然、文字起こしに基づく議事録が必要とされたでしょう。そのような会議の参加メンバーは、多くの場合、要職にある方々と思われます。そして、当事者のみなさまからは議事録の作成に関して、「機密情報の漏洩を防ぐため、部下に任せられず、自分でせざるを得ない」といったお話をよく伺います。
文字起こしのように非創造的な労働にマンパワーを浪費してしまうことは、職位の高低を問わず得策ではありません。Web会議に切り替えることで、移動・時間・場所のコストを節減できるはずですので、それを文字起こしと議事録作成の負荷軽減に振り向けるべきです。
その結果、これまで文字起こしと議事録作成の作業に消耗させられていた人材が本来業務に専念できれば、業績の向上に寄与することを期待できます。イノベーションを起こして新商品・新サービスを開発したり、新規顧客を開拓・新規案件を受注できたりすれば、Web会議システムの導入や、議事録作成の効率化にかかるコストを補って余りある収益増をもたらすことでしょう。
5. Web会議の議事録作成と文字起こしを効率化する方法
5-1. 議事録作成支援システムを導入する
議事録作成支援システムには、既存のWeb会議システムに連動させて利用するものと、Web会議システム自体に組み込まれているものがあります。インターネットで「議事録作成支援」を検索すると、様々なサービスを探すことができます。
多くは、人工知能(AI)による音声認識で文字起こしを自動化する機能を備えています。AI音声認識はどうしても誤認識が発生するので、人の手による修正を必要としますが、その作業をしやすいようにエディターが工夫されています。
例えば、リアルタイム音声認識の文字起こしで自動生成される文字列を、会議の参加者がその場で確認して誤認識の部分に印をつけておき、会議後にその部分だけ録音を再生しながら効率良く修正できたりします。
このほか、キーワードの抽出や要約、多言語への翻訳など、多機能化も進んでいます。上手に使いこなせれば、文字起こしと議事録作成の大幅な省力化につながるでしょう。
ただし、あくまで省力化であって、完全に無人化できるわけではないことには注意が必要です。
5-2. 文字起こしの専門業者に外注する
議事録作成を専門業者に外注してしまえば、文字起こしと議事録作成という創造性のない仕事にマンパワーを割く無駄を、事実上、解消できるでしょう。仕上がりの仕様や体裁、要約の要否を含め、専門業者であればきめ細かな対応を期待できます。
価格の安さ、納期の速さ、得意とする領域、外国語対応、情報セキュリティの堅さなど、専門業者にはそれぞれに特色があります。利用料金は議事録作成支援システムに比べて割高となりますが、Web会議に切り替えて節減できたコストの範囲内に収まる可能性があります。仮に収まらなかったとしても、文字起こしや議事録作成から解放された人材が本来業務で創造的な仕事を成し遂げたならば、十分に元は取れるでしょう。
Web会議のレコーディング機能は大変便利ですが、その録画ファイルや録音ファイルをそのまま受け付けて議事録にしてくれる専門業者もあります。
6. 問われる経営判断
Web会議に切り替えて、移動にかかるコストを削減できる分を、議事録作成支援システムに投資してさらなるコスト削減を堅実に積み重ねるか。それとも、割高な専門業者に外注してコスト削減効果が相殺されても、議事録作成から解放された人材に創造的な仕事をしてもらうことによる無限の可能性に期待するか。
いずれにせよ、この国では生産年齢人口の減少が加速し、人材確保が年を追うごとに困難となります。意思決定する立場にある方は、こうした外部環境の変化も勘案したうえで、議事録作成においても賢明な打ち手を講じておく必要がありそうです。