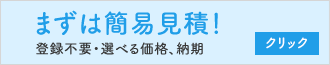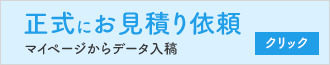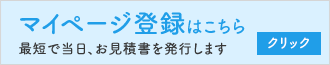言い間違いをどこまで直す? 正確な文字起こしであるために
話し手が言い間違えても、聞き手との間で文脈や場の空気感が共有されていれば、誤解なく意思疎通できるでしょう。ところが、そのまま文字に起こすと支障が生じるおそれのある場合、反訳者が手を加え得る許容範囲はどこまでなのでしょうか。

目次
1. 反訳者によるやり過ぎは厳禁
文字起こしをしていて話し手の言い間違いに気づいたとき、国語力に自信のある反訳者ほど、過剰な訂正をしがちです。確かに、誤った日本語のままだと、「この反訳者は日本語を知らないな」と思わるのではないかという不安が残ります。
しかし、反訳者の仕事は自分の国語力をひけらかすことではなく、一にも二にも「音声を文字化」することです。依頼主から特に指示がない限り、簡単な訂正は「おまけ」のようなものです。だから、やり過ぎは絶対厳禁なのです。
2. 単純な間違いは訂正する
反訳作業を行う上で、「単純な言い間違いは訂正する」というルールがあります。例えば、「令和」を「平成」と言ってしまったり、誰が考えても話し手のうっかりミスだったりする場合は、文字起こしの時点で修正しても構わないとされています。
実際に、数字の読み間違いなどはしばしばあるものです。文字起こしの依頼主から点検用の資料が提供されている場合には、その資料に従って適宜正しく直します。そのように依頼主から求められることも少なくありません。

3. 判断に迷ったときは音どおり文字に起こす
一方で、反訳者の間には「(判断に)迷ったときは音どおり」という格言があります。「単純なミス」かどうか自信が持てないときは、念のため音声どおり文字に起こします。その部分の処理は、依頼主の判断に委ねるのです。
また、規則に厳格な会議では、正式な手続を踏んで「発言の訂正」が行われることがあります。その場合はもちろん、一旦間違えた発言のまま反訳し、後の訂正手続も含めて全て文字化することになります。
4. 特に注意を要する反訳
会議や講演会などは、割と幅広く反訳者の判断で訂正が許されているのですが、特殊な場合として注意しなければならないのは、裁判の尋問調書の文字起こしです。

調書作成時には、「単純な言い間違い」の線引きが極めて微妙になってきます。それは、「言い間違い自体に何らかの意味」があり、後でその発言が問題になる場合があるからです。言い間違いについては、精神分析学の創始者として知られるフロイト(Sigmund Freud、1856-1939)が、単なる不注意ではなく、無意識の本音や願望のあらわれである可能性を指摘しています。
このため、相手方の弁護士から「はっきり覚えているという割には記憶が曖昧ではないか」などと攻撃されることもあり、それにどう答えるかが証言の信ぴょう性に関わってくることもあります。ですので、「迷ったときは音どおり」の原則を常に意識する必要があります。
5. 話し手が自信満々なのに言い間違えていたら
文字起こしをしていて困るのは、話し手が「単純に言い間違えた」のではなく、「確信して言い間違えた」ときです。例えば、漢字の読みや慣用表現を勘違いして覚えていて、自信満々で誤用していたら……。それも社会的立場があり、それなりに尊敬されるような人だったら……。
「うる覚え」「的を得る」といったワンフレーズ程度なら、反訳段階で「うろ覚え」「的を射る」という正しい表現に直します。これに対して、一文にわたるような複雑な誤用は、「迷ったときは音どおり」の原則に則り、敢えて間違えたまま文字に起こします。気を利かせて直し過ぎると、「創作・編集」になってしまうためです。
人名・地名などの言い間違いも頻繁にあります。これも、話し手の意図するところがちゃんとつかめて、きちんと裏づけが取れるなら、反訳する段階で訂正します。はっきり分からない場合は、やはり「迷ったときは音どおり」にするのが無難です。
6. 文字起こしの依頼主ごとに要求水準を見極めよう
通常、文字起こしをした原稿がいったん出来上がったら依頼主に見てもらい、依頼主が赤字で加筆・修正したものが反訳者の手元に戻ってきます。このときに、「どういった点をどこまで依頼主が修正しているか」をチェックしておくと、次回からの作業のときに、反訳者の裁量に許される範囲をある程度見定めることができます。
要求されるレベルは、依頼主ごとにまちまちなので注意が必要です。